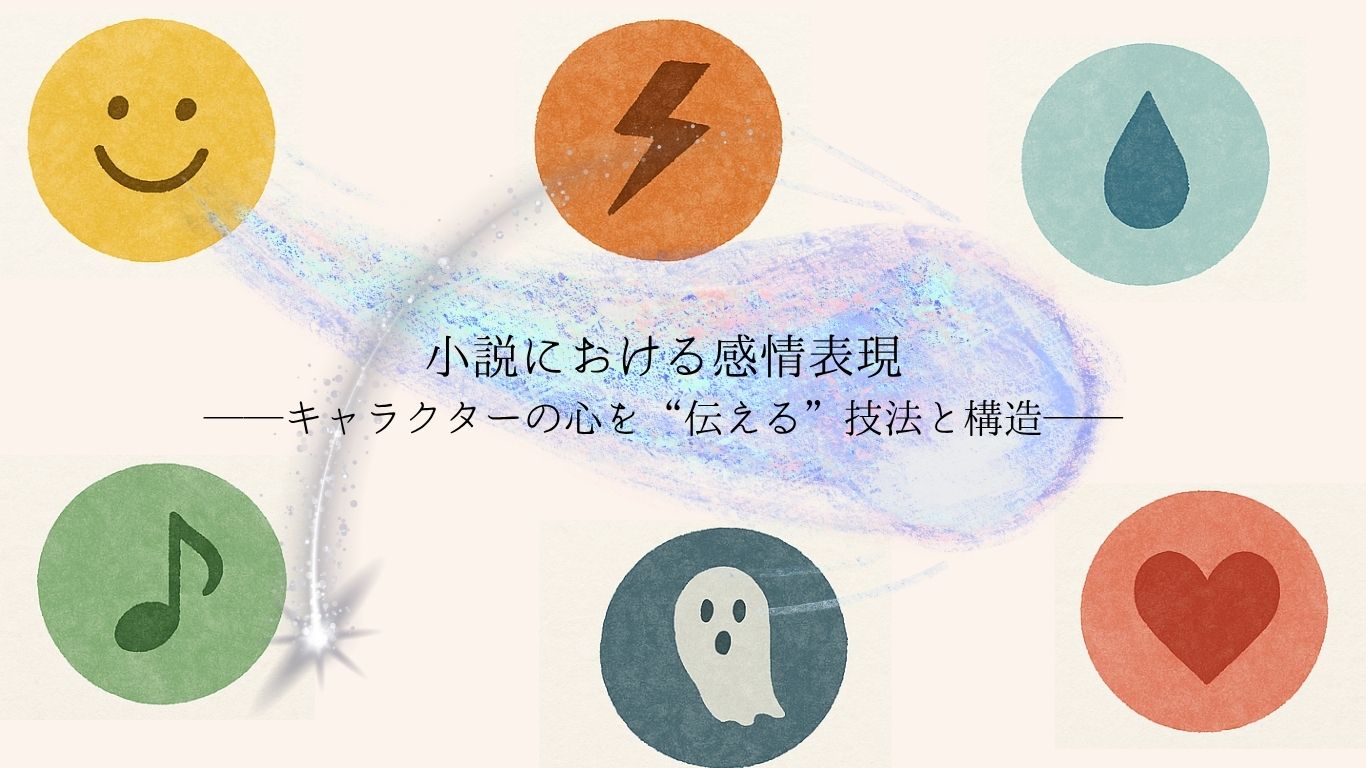小説とは、感情を描く媒体である。
にもかかわらず──感情表現は、最もつまずきやすい技法でもある。
怒っているのか、泣いているのか、迷っているのか。「嬉しい」と書けば嬉しさが伝わるわけではない。「悲しい」と書けば、読者が同じ悲しみを味わってくれるわけでもない。
それでは、どうすればキャラクターの“心”を伝えられるのだろうか?
本記事では、「感情表現」という曖昧で繊細な領域を、構造的に捉える視点を整理する。
「感情」は表現されて初めて“共有”される。
小説における感情表現は、主に以下の三つの構成要素に分解できる。
① 感情の種類(何を感じているか)
感情は十人十色。しかし、ここでは小説で描かれやすい代表的なものをまとめておく。
- 喜:笑い・跳ね・軽快な動き
- 怒:語気・拳・速度・沈黙
- 哀:視線・背中・沈みゆく空気
- 楽:遊び・緩み・他者とのつながり
- 恐:汗・目線・物理的距離の変化
- 愛:視点の集中・対象への小さな描写の積み重ね
言葉で直接的に書かれることもあるが、むしろ「行動」や「環境」といった周辺情報ににじませる表現が効果的とも言えるかもしれない。
② 感情の伝達方法(どう見せるか)
- セリフ:言葉遣い・テンポ・呼びかけ
- 動作:歩き方・仕草・視線・ため息
- 身体反応:鼓動・震え・皮膚感覚
- 風景との照応:雨、光、季節、時間帯
- 他キャラとの関係性変化:距離、気配、視線の交差
③ 読者への響かせ方(どこに置くか)
- 感情を“溜めてから出す”構成
- 感情を“断片化して積む”設計
- 感情を“他者の視点から”浮かび上がらせる手法
このように、感情とは「言葉」ではなく「設計」で伝えるもの。
次章では、実例を通してその技法を具体的に検証していく。
読者への響かせ方を検証してみる。
本項では一般論の内容から、特に読者への響かせ方について掘り下げていきたい。
感情を“溜めてから出す”構成
感情を溜めるという状況は、相手(もしくは自分)が表面上および実際の心情が真逆の時に現れると推察される。そこで、以下の例文を見ていただきたい。
例文①:溜めてから出す構成
由里はにこやかにパートナーの話を聞いていた。浮気の理由、仕方ないとの言い訳。気付けば、指がカタカタ動いていた。しかし口角を無理に上げて、柔和な表情を貫いた。すると、彼が言う。
「だから、あれは事故だったんだ」
そして彼女は眉間のシワを最大限に伸ばして言葉にする。
「今すぐ、私の前から消えてくれる?」
その時、すでに由里の微笑みは消えていた。
上記は、にこやかな由里が指や口角などの体の動きで徐々に怒りをあらわにし、言葉によって爆発させる構成である。
すると、由里の冷静な怒りや、相手を見限ったであろう心情が伝わるのではないだろうか。
このように、感情を溜めてから出す構成は言葉や主だった行動で示すのではなく、僅かな所作を積み重ねて結末を迎える構成になると考えられる。
感情を“断片化して積む”設計
例文①を“感情を断片化して積む”設計にしてみると、どうなるだろうか?
以下の例文を見ていただきたい。
例文②:断片化して積む設計
由里はにこやかにパートナーの話に耳を傾けた。
「あの時の事は、酔っぱらっていて覚えていないんだ」
——覚えていなかったら、何をしてもいいんだ。でも……。
「それに誘ってきたのは、アイツで俺じゃない」
——覚えてんじゃん。嘘つき。
「だから、あれは事故だったんだ」
——あくまで相手のせい?嫌い。
そして彼女は眉間のシワを最大限に伸ばして言葉にする。
「今すぐ、私の前から消えてくれる?」
その時、すでに由里の微笑みは消えていた。
上記では、由里の気持ちがパートナーの会話ごとに、“でも……(好意)”→“嘘つき(疑念)”→“嫌い”というように変化していることが分かる。
このように、感情の変化を断片的に明示すると、例文①の由里とは違い、より感情的な人物像が見えてきたのではないだろうか?
つまり、感情を断片化して積む設計を用いると、人物の感情が鮮明に伝わり、愛嬌のあるキャラクターになるとも言えるかもしれない。
感情を“他者の視点から”浮かび上がらせる手法
最後に他者の視点から浮かび上がらせる手法として、パートナー側から由里の心情を探ってみたいと思う。
例文③:他者の視点を使った場合
目の前の由里は微笑んでいる。俺の話を聞き入れてくれる気配もある。そこで、俺は浮気の理由を詳しく話した。
由里は未だに微笑んでいる。怒っているのか、許してくれているのかは、まるで分らない。しかし、彼女の表情はぎこちない。そこで俺は強くでることにした。
「だから、あれは事故だったんだ」
そう言うと、由里の表情がゆっくり崩れてゆく。そして彼女が口を開く。
「今すぐ、私の前から消えてくれる?」
その時、すでに由里の微笑みは消えていた。
上記では、由里が穏やかなまま、パートナーの言葉を引き出している様子が浮かび上がっているのではないだろうか。また、パートナー(俺)の観察眼の乏しさや思慮の浅さも同時に垣間見られる。
このように、感情を他者の視点から浮かび上がらせると、視点人物および相手の心情や人物像が良く見えるようになると言えるかもしれない。
なお、以下の記事では小説における表現についてまとめています。
おわりに
今回は、小説における感情表現と題して、一般的な情報をまとめて、読者への響かせ方を検証した。
響かせ方は伝え方によって色が変わる。つまり——
- 感情を“溜めてから出す”構成→冷静な感情表現
- 感情を“断片化して積む”設計→鮮明な感情表現
- 感情を“他者の視点から”浮かび上がらせる手法→キャラクター性が滲む感情表現
とも言えるだろう。しかしながら、上記は一例に過ぎない。組み合わせを少し変えるだけで、さまざまなケースにも対応できる。
そこで、最後に一言。
「あなたはどうやって感情を届けたいですか?」
そう考えると、作中に十人十色を彩れるかもしれない。
以上