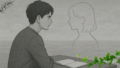物語を考えるとき、最初に「何を決めるか」は人によって違う。
キャラから入る人もいれば、場面から入る人もいる。
けれど、“話の土台”が曖昧なまま書き始めると、途中で物語が崩れやすい。
この記事では、「ストーリー設定」とは何か?という基本から、設定をどう構造化することで物語を支えるか、その考え方の土台を整理していく。
「なんとなく書いていると破綻する」──そんな人に向けて、設定を“意味ある骨組み”にするための出発点になればと思う。
一般論:ストーリー設定の基本的な役割
“ストーリー設定”という言葉は人によって捉え方が異なる。しかし、一般的には物語の背景・ルール・前提・出来事の土台を支える情報のことを指す。
たとえば、舞台設定(時代・場所・社会)、世界観(魔法・技術・秩序)、主人公の立場や制約などが含まれる。
これらの設定は、プロットの展開やキャラクターの行動に説得力を与えるための“前提条件”として重要である。特にファンタジーやSFのように非現実的な物語では、設定が曖昧だと読者の没入が阻害されやすい。
また、設定は“演出のための装飾”ではなく、テーマや物語構造を支える機能も持っている。たとえば「階級社会」という設定は、単なる背景ではなく、キャラの選択や葛藤の根幹に関わってくる。
つまり、ストーリー設定とは“物語を支える見えない構造材”であり、読者が自然に世界に入れるようにする“静かな設計”なのだ。
考察①:ストーリーとは“差分を埋める”もの?
ストーリーについて、筆者は“差分を埋める”行為だと考えている。なぜなら、人は変化に対して敏感で、目標に向かう事柄――つまり“差分を埋める”過程に興味を持ったり、時には恐怖したりと、さまざまな感情をあらわにするからである。
たとえば、数あるストーリーの中でも“成り上がり”ストーリーが王道かもしれない。不良少年が起業して成功したり、落ちこぼれがエリートと戦って勝利したりと……。他にも“転落”ストーリーもある種、人気があるかもしれない。王族の没落、成金の破産など……。
これらは全て、読者(筆者も含めて)は物語が進むにつれて、キャラクターの変化や葛藤、はたまた環境の変化などを通して過程を楽しみ、しだいに感情が動かされているのである。
つまり、ストーリーとは物語におけるゴールとの“差分を埋める”ことによって、読者の感情を動かす舞台装置だと言えるかもしれない。
考察②:ストーリーを支える論理と共感とは?
ストーリーに大事なこと――これは、読者によってさまざまである。共感をもとめる人もいれば、論理をもとめる人もいる。一概に、どれが正解ということもないのだ。
しかしながら、筆者としてあえて言葉にするなら、『論理と共感の比率』が大事だということになるだろう。
たとえば、論理100%・共感0%だとすると、これは論文なのである。整然とした論理が並び、心を動かすというよりは頭を動かすという方が近いかもしれない。
逆に、論理0%・共感100%の場合、もはや自然現象の観測なのである。確かに、自然現象によって心が動くこともあるかもしれない。しかしながら、ただ漠然と現象があるのではなく、文章の流れ、観測までの待ち時間、視界の美しさなど、論理だったストーリーが少なからず存在するのである。
つまり、『論理と共感の比率』をどうブレンドするかによって、感動系や推理系などさまざまなストーリーに変化させることができると考えられる。
考察③:背景が語るものとは?
背景設定について、筆者は必要だと考えている。本文中には登場しなくとも、少なくとも筆者は知っておくべきだと思っている。理由は、筆者として知っていることによりキャラクターにも歴史ができ、キャラクターの思考の系譜ができあがるからである。
たとえば、DEATH NOTEの夜神月も社会背景があるからDEATH NOTEを使う動機となる。Hunter×Hunterのゴンも父(ジン)がいないことにより強い憧れを持つようになるなど、背景設定がキャラクターの個性と成りうるのである。
そのため、筆者としてはファンタジーであれば歴史年表や世界地図を作る必要もあるだろうし、現代モノであれば実在する制度や実情などの取材も必要だと考える。
つまり、ストーリーは本編だけのものではなく、ストーリーの前後(特に前)から始まるものだと考える必要があると言えるだろう。
おわりに
今回は、ストーリー設定について考察していった。
筆者にとってのストーリーの土台は、
- 物語における目標との“差分を埋める”ために
- “論理と共感の比率”をブレンドしつつ
- 背景から深みを出す
ということに集約されると考えている。
では、ここで一言。
「あなたはどんな物語に心が動きますか?」
その動きの中に、あなたの設定があるのかもしれない。
以上