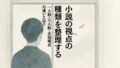登場人物の心の動きを描く──それは小説において最も難しく、同時に最も魅力的な要素である。
感情の揺れ、言葉にできない戸惑い、無意識の選択。
心理描写とは、読者が物語に“深く沈む”ための導線であり、単なる心情の説明ではない。
本記事では、小説における心理描写の基本的な技法(直接描写と間接描写)の違いを整理しつつ、筆者がどのように考えて、どのような書き方をしているかを紐解いていく。
なお、以下の記事では小説における表現をまとめています。
直接描写と間接描写の違い
心理描写とは、登場人物の内面、すなわち感情や思考、葛藤などを描く表現技法である。
大きく分けると「直接描写」と「間接描写」の2種類がある。
- 直接描写
この描写方法は「彼は怒っていた」「悲しみに包まれていた」など、感情を明示するために用いられる。そのため、一人称や感情主導の場面に向いている手法だといえる。 - 間接描写
この描写方法は、表情・動作・比喩・環境描写などを通して内面を浮かび上がらせるために用いられる。たとえば「彼はグラスを強く握りしめた」と表現して怒りを示すなど、読者に“察してもらう”構造になるかもしれない。
心理描写が優れている文章は、キャラクターに“息遣い”を与え、読者の感情を自然に引き込むことができる。
ただし、描きすぎると読者の想像を奪い、描かなさすぎると共感を生みにくくなるため、描写の位置づけや、直接描写と間接描写のバランスが重要となると言えるだろう。
心理描写を例文で見る①:直接描写を描くシーン
筆者が考える直接描写を描くシーン。それは、キャラクターの心情が大きく、もしくは激しく動くときである。なぜならば、「喜び」「怒り」「哀しみ」「楽しい」などの直接描写は、文字そのものに意味を持っており、より強く伝わると考えられるからである。
しかしながら、筆者は人が喜怒哀楽を明確に示すシーンはそこまで多くないように思えてしまう。(筆者だけかもしれないが……)
たとえば、『自分が躓いたシーン』を考えてみよう。
自分が躓いたシーン(直接描写)
私は地面に落ちていた空き缶に躓いた。見ると、パンツの膝の部分が破けている。そして、思ったのだ。誰が空き缶をポイ捨てしたのか?なぜ空き缶くらいで躓いたのか?
すると、激しい怒りと悲しみが舞い上がってきて、胸をもやもやとさせる。だから――。
このように『自分が躓いたシーン』では、自分もしくは躓いた原因に対する感情(「怒り」や「悲しみ」など)が表れやすい状況かもしれない。
そのため、上記のようにキャラクターの感情がはっきり表れやすいシーンでは、直接描写の方がより伝わりやすいと考えられる。
心理描写を例文で見る②:間接描写を描くシーン
では、間接描写はどうだろう。筆者は、人の持つ曖昧さやじわじわと昇ってくる感情にこそ間接描写が有効ではないかと考えている。理由は、キャラクター自身も自分の感情をはっきりと把握していないからに他ならない。
例として、『誰かが躓いたシーン』を考えてみたい。
誰かが躓いたシーン(間接描写)
私が道を歩いていると、前を歩く見知らぬ男性が転んだ。どうやら空き缶に躓いたらしい。私は彼を横切りながら思った。誰が空き缶をポイ捨てしたのか?子供や老人が躓けばケガだけでは済まないのでは?
そう思うと、重くて、冷たい何かが胸の中に漂い始めた。そこで私は空を見上げて、息を吐いた。すると吐息が雨雲に吸い込まれていった。
上記のシーンでは、主人公(=私)が直情的に「怒り」や「悲しみ」を露わにしにくいのではないかと予想する。(キャラクターの文脈や性格としての直接表現は効果的なのだが……
そのため、キャラクターの曖昧な気持ちや湧き上がる感情などを静的に表したいときに間接描写が有効だと考えられる。
心理描写を例文で見る③:直接描写、間接描写をあわせ持つ書き方は?
実を言うと、筆者は「直接描写」と「間接描写」のどちらかの派閥に入っている訳ではない。それこそ、シーンやキャラクターの個性によって使い分けているのである。
例として、『彼女が躓いたシーン』を考えてみよう。
彼女が躓いたシーン(直接描写)
私が彼女と歩いていると、彼女が空き缶に躓いた。見ると彼女のパンツの膝の部分が破けている。すると、彼女はすぐさま怒りを露わにした。それを見た私も空き缶やポイ捨てをした誰かに怒りが込み上げてきた。
上記は、彼女が躓くことにより、私と彼女の感情を直接描写で書いてみた。すると、私が彼女の感情に同調している姿が伝わるのではないだろうか?
そこで、次は間接描写を使って書いてみようと思う。
彼女が躓いたシーン(間接描写)
私が彼女と歩いていると、彼女が空き缶に躓いた。見ると彼女のパンツの膝の部分が破けている。彼女は破れたパンツを見ながら、唇を震わせ始める。それを見た私も空き缶やポイ捨てをした誰かに声を荒げたい気持ちになった。
上記はどうだろうか?今度は彼女の感情に不安定さが垣間見える。きっと、ストーリーやキャラクターの個性に何かしらの文脈があるのかもしれない。しかしながら、それがない場合は、不自然さが際立つ構図になり得ると考えられる。
では、直接描写と間接描写を混ぜてみるとどうだろう?
彼女が躓いたシーン(直接描写+間接描写)
私が彼女と歩いていると、彼女が空き缶に躓いた。見ると彼女のパンツの膝の部分が破けている。すると、彼女はすぐさま怒りを露わにした。それを見た私も空き缶やポイ捨てをした誰かに声を荒げたい気持ちになった。
上記は、彼女の感情を直接描写で描き、私の感情を間接描写で描いてみた。すると、直情的な彼女と、彼女に反応して感情が湧いてくる私が、より鮮明に描写されているのではないかと思われる。
このように直接描写と間接描写は、それらをバランスよく混ぜ合わせることで、シーンの緩急やキャラクターの心情を際立たせる効果があると言えるだろう。
まとめ
今回は、小説における心理描写として、「直接描写」と「間接描写」の違いや使いどころなどをまとめてみた。
筆者の作品は「間接描写」が多いと自覚している。そのため、「直接描写」の割合も増やしていければという思いもあって、本記事を執筆した。
そして分かったことは、「直接描写」が好きという方も、「間接描写」が得意という方も、両者をうまくブレンドすると、より感情の豊かなシーンやキャラクターになるかもしれないということである。
では、最後に一言。
『あなたはどちらの心理描写が好きですか?』
それを知るだけで、より豊かな物語が描けるはず。
以上
👉これまでの作品一覧。