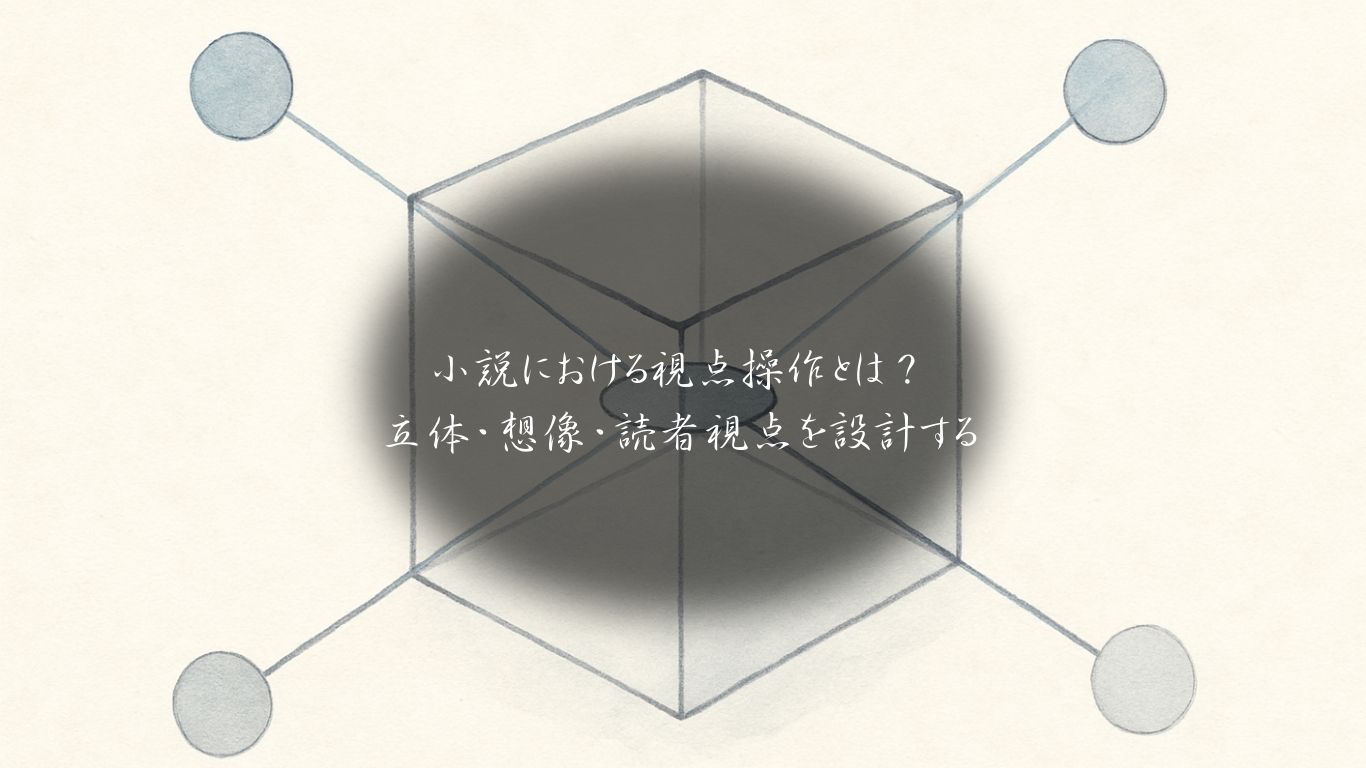誰の目で、どこから、何を見せるのか。
小説の視点は、単なる語り方の選択ではなく、物語の空間をどう設計するかを決める“読者体験の装置”でもある。
筆者は物語を書くとき、視点操作を“構造設計”の一部として使っている。それは、ただの多視点ではない。たとえば、同じ空間にいる二人の視点を切り替え、シーンを立体的に見せたりするのだ。
この記事では、筆者が意識的に使っている「立体的視点操作」「想像的視点操作」「読者視点操作」について、一般的な視点の基礎を踏まえながら、筆者なりの思考を整理してみたい。
一般論:小説における視点の基本と、筆者のとらえ方
小説における視点は、大きく分けると一人称視点および三人称視点がある。
一般に、一人称は没入感が強いが、視野が狭くなる。三人称は登場人物の外側から描きつつ、特定キャラの内面に寄り添える特徴があるとされている。
また、三人称視点には以下の種類がある。
- 三人称限定視点
- 三人称多視点
- 全知視点
上記を簡単に述べると、三人称限定視点では一人称に近い心情表現と外郭をあわせ持つ。三人称多視点では複数キャラの視点を切り替え、群像劇などに適する。そして全知視点では神の視点から語り、広い世界を描けるが、距離が遠くなりやすい。と言った特徴がある。
小説の視点における詳しい内容は、以下の記事に記載しているので、あわせてご覧いただきたい。
筆者が特に使うのは三人称限定視点である。しかし、それを三人称多視点的に使ったり、一人称視点寄りに使ったりとさまざまな手法を試みている。ここで重要なのは、“ただ視点を並べる”のではなく、“構造として配置する”ことだと考えている。
つまりは視点を用いた操作――視点操作は、読者にどこを見せ、どこを見せないかを計算する“視線の設計”であり、物語の奥行きやズレを生み出すための装置だと言えるだろう。
小説における視点操作の考察
筆者が小説を書く際に、以下の視点操作を用いてシーンを描いている。
- 立体的視点操作:映像的にシーンを見せたい時に使用
- 想像的視点操作:視点人物から明らかに見えないシーンを補完するために使用
- 読者視線操作:読者と各キャラクターのみが知る情報から伏線や謎を作る時に使用
本項では、上記3つの視点操作の考察をまとめていく。
考察①:立体的視点操作
筆者は複数人が同時に動くケースで、立体的視点操作をよく用いる。具体的には、①相手に直接向かい合う人物と、それらの様子を②一歩引いた位置で見ている人物を分けて登場させる。
この場合、①の視点では相手との直接的なやり取りを、②の視点では①の人物の周りの状況を含めて描くのである。
例として、『ボクシングの様子』を描いてみよう。この場合の登場人物はボクサーAとセコンドB、そして対戦相手となると予想される。
【ボクサーAの視点】
ゴングの音が聞こえた。対戦相手は両手で頭を守りながら、間合いを詰めようと試みている。足音がした。相手の拳が顔面に襲い掛かる。ボクサーAはそれをかわして、拳を相手の顎に目がけて打つ。
【セコンドAの視点】
ボクサーAと対戦相手は一進一退の攻防を繰り広げている。しかし、どちらの拳も僅かに相手に届かない。時間が少なくなってきた。観客席からの声援が大きくなる。
ボクサーAが少しよろけた。対戦相手はすぐさま彼の隙を突く。しかし、ボクサーAは――。
というように、視点を分けて描くと、登場人物の具体的なやりとりと、周囲の環境を映像的に描けているとわかるのではないだろうか。
つまり、筆者が考える立体的視点操作は以下のようにまとめられる。
- 同じシーンに登場する二人以上の視点を切り替えると、
- 心理の温度差、空間の奥行きを「同時進行的に演出」でき、
- 読者に「より映像的な体験」を提供できる。
と、考えている。
考察②:想像的視点操作
筆者が想像的視線操作を用いる時。それは登場人物の視界では明らかに見えないシーンを、人物の想像によって読者に伝えたい時である。
以下は、考察①の『ボクシングの様子』で文章を書いたものである。
【想像的視点操作の例】
――ボクサーAはそれをかわして、拳を相手の顎に目がけて打つ。
観客の声援が聞こえる。セコンドAもタオルを片手に、声をあげているに違いない。ボクサーAはセコンドAのためにも勝利をもぎ取りたいと強く思った。
このように、ボクサーAからはセコンドAは見えていない。しかしながら、ボクサーAがセコンドAへの思いを巡らすことで、セコンドAの様子を間接的に読者に伝えているのである。
つまり、想像的視点操作は以下のようにまとめられる。
- 視点人物が「心の中」で、
- 「見えていない状況」に思いを巡らせ、
- 読者に「周囲の状況」を伝える
と、言えるだろう。
考察③:読者視点操作
筆者が読者視点操作を使うときは、たいてい伏線や謎を残したい時である。
例として、考察①②で使用した『ボクシングの様子』をセコンドAの視点とボクサーAの視点で書いてみたい。
【読者視点操作の例】
(セコンドAの視点)
セコンドAの視線の先には、ボクサーAと対戦相手が見えている。彼らはどちらも決め手に欠け、勝負を決しようとしない。
時間が迫る。セコンドAの額にも汗がにじんでくる。すると、相手セコンドの手が大げさに動いた。まるで何かを投げたような仕草。その瞬間、ボクサーAがよろけたのである。
(ボクサーAの視点)
脇腹に衝撃があった。ボクサーAはそれにより、少し体勢を崩してしまう。しかし彼には関係のない事であった。一瞬の揺らぎ、彼はそれを利用して相手を誘い、カウンターを狙ったのである。
上の例では、読者とセコンドAには相手セコンドが何かをした(かもしれない)ことがわかる。しかしながら、ボクサーAは気が付いていない。
そのため、相手のセコンドが何をしたのか?という謎が読者とセコンドAだけに残る構図となるのである。
つまり、読者視点操作とは以下のようにまとめられる。
- 読者(および特定のキャラクター)だけが知っている情報で、
- 各キャラクターの行動に“ズレ”を生じさせ、
- それらを積み重ねていくことで、読者とキャラクターとのズレを作りだす。
と、言えるかもしれない。
おわりに
今回は、視点操作と題して、筆者が使っている視点の使い方を考察してみた。
筆者は、作中における視点操作を『小説を映像的に描く』ため、そして『読者に“ズレ”や“謎”を残す』ために使用している。
しかしながら、視点の変動が多すぎると、読者が戸惑う種になることは否めない。そこで、各話ごと(もしくは、かたまり毎)に配慮しながら書き進めると良いかもしれない。
すると、あなたの思い描く面白いシーンが描けるはず。そう信じて、本記事を締め括ろうと思う。
以上