小説の書き方で、最初に迷うことの一つが「視点の選び方」かもしれない。
『誰の目で、どこから物語を見るのか?』
その選択によって、語り口も、読者との距離も、登場人物の見え方も変わってしまう。
また、視点とは語りのスタイルであると同時に、書き手の「どこに立つか」という構造でもある。
今回は、小説の視点について基本を整理しながら、一人称と三人称の違いに込められた“物語との距離”を筆者なりに考察していく。
小説の視点の種類―― 一人称、三人称の違い
小説における視点は、大きく分けて2つに分類される。
- 一人称視点:主人公自身の語りで物語が進む視点。
読者は主人公の思考や感情を直接知ることができるが、主人公が知らないことは描写できない制約がある。そのため没入感は強いが、視野は狭くなる。
- 三人称視点:語り手が登場人物を“外から”描写するスタイル。
この中にも複数の型が存在する。
・三人称限定視点(主人公視点)
1人のキャラクターの内面に寄り添いながら、三人称で物語が進む。一人称に近い距離感を保ちながらも、キャラクターの見えない部分を外側から描くこともできる。
・三人称多視点
物語の章ごと、シーンごとに複数キャラクターの視点を切り替える方法。群像劇や複数の登場人物の内面を描きたい場合に用いられる。ただし、切り替えのルールが曖昧だと読者を混乱させるリスクがある。
・全知視点
すべてを知る語り手(神の視点)が物語を語る。登場人物すべての内面、背景、未来までを語ることができるが、視点の距離が広がりすぎるため、読者の没入感が薄れる危険もある。
このように、小説における視点は単なる語り口ではなく、物語の距離感や読者への情報開示のルールそのものでもある。そのため作品のテーマや狙いに合わせて、適切な視点を選ぶことが重要になる。
【用語メモ】
三人称限定視点は、古い批評用語では「三人称一元視点」と呼ばれることもある。両者はほぼ同義だが、近年では「三人称限定視点」という表現の方が一般的であり、本記事でもそちらで統一している。
【番外編】二人称視点
読者自身を登場人物として扱い、「あなたは〜」と語りかけるスタイル。
特殊な形式であり、実験的な文学やゲーム小説、詩的な文章で使われることが多い。没入感が高いが、読者を選ぶ手法ともいえる。
考察①:なぜ三人称限定視点が書きやすいと言われるのか?
三人称限定視点が書きやすいと言われる理由。それは、地の文(会話文以外の文章)に全体描写を挿入しても、不自然になりにくいからだと考えられる。
さらには、作者が視点人物(主人公など)に寄り添いながらも、ある程度“外側”の状況を伝えることができる点も理由の一つかもしれない。
例として、一人称視点および三人称限定視点で、“曇天の空に鳥が飛んでいる”様子を描写してみよう。
【一人称視点の場合】
私は曇天の空を見た。そこには白い鳥が優雅に羽ばたいている。彼はどこに向かうのだろうか?なんて思いをはせながら、そっと目を閉じたのだった。
【三人称限定視点の場合】
太郎は空を見上げた。そこには白い鳥が羽ばたいている。
(彼はどこに向かうのだろうか?)
そう思いながら、太郎は目を閉じた。そして白い鳥は曇天に消えていったのだった。
上記のように、一人称では視点人物(=主人公)が“曇天の空を見た”という描写が必要になる。なぜなら、語り手が主人公本人なので、彼/彼女が「見たこと」しか描けないからである。
一方、三人称限定視点では、視点人物の頭上にカメラが浮いているようなイメージで書くことができる。そのため、視点人物(太郎)が目を閉じた後でも、“空の様子”を読者に伝えることができる。
そのため、三人称限定視点は、以下のようなケースに有効な手法だと言えるかもしれない。
- 視点人物の環境と感情を同時に描きたいとき
→人間ドラマ、心理劇など - 読者に“自然な没入感”を与えつつ、情報を制御したいとき
→ミステリー、サスペンスなど - 作者と主人公の思想を強く示すことなく、感情には寄り添いたいとき
→恋愛小説、ファンタジーなど
このように、三人称限定視点は多くのジャンルに精通しており、「主観と客観のバランスをとりやすい」ため、書きやすいと感じると考えられる。
考察②:一人称視点のメリットは?
一人称視点のメリット。それは、地の文に視点人物の感情をそのまま落とし込めることだと考えられる。
例として、考察①で用いた「鳥の描写」を、『主人公が白い鳥を見て、希望を抱き、前向きになる』という内容に拡張してみよう。
【一人称視点の場合】
私は曇天の空を見た。それは、まるで私の心の中を見透かしているように灰色に淀んでいる。
白い鳥が優雅に羽ばたいているのが見えた。彼はどこに向かうのだろうか?──そんな思いをはせていると、ふわっと心が晴れていくのがわかった。そして、私はそっと目を閉じたのだった。
【三人称限定視点の場合】
太郎は空を見上げた。そこには白い鳥が羽ばたいている。
(彼はどこに向かうのだろうか?)
太郎はそう思うと、心が軽くなるのを感じた。そして彼は目を閉じた。空は、いつのまにか曇天から晴れへと変わっていった。
上記のように、三人称限定視点では、風景描写と感情描写を分けて表現していることがわかる。これは、地の文と感情文を用いて視点人物の行動・感覚に寄り添いながら感情を描写し、後に続く風景描写の文とリンクさせているのである。
つまり、「人物が感じたこと」「空の変化」といった情報を、文中で“整理して届ける”構造になっていると言えるだろう。
一方、一人称視点では、風景描写と感情描写が混ざり合うように描かれていることに気がつくかもしれない。これは、「空の変化」と「人物が感じたこと」を重ねて、主観的な表現へと導いていることに他ならない。
このように、一人称視点は感情と風景を一体化させやすいことから、
- 深い内面描写をしたいとき
→純文学、私小説など - 登場人物の心の動きに焦点を当てたいとき
→日常系ラブストーリー、感情の成長譚など - 心情的な文体をとりたいとき
→エッセイなど
に、特に有効な視点構造だと考えられる。
なお、小説における「視点」そのものの考え方や、種類・失敗例・構造的な整理については、以下の記事で総合的に解説しています。
まとめ
今回は、小説における視点について掘り下げていった。視点の書き分けというのは、実に奥深く、明確な正解がないのも事実である。
そこで、筆者があえて区別を言語化すると、以下のようになる。
一人称視点は、『主人公の心そのものが語る』ような文体。
三人称限定視点は、『誰かが人物の心を通訳する』ような文体。
だと、言うことが出来るかもしれない。つまりは、視点とは物語の語り口であり、書き手がどこに立って、何を見つめているかの表明でもあると言えるだろう。
なお、視点の選び方については、本記事ではあえて触れていない。なぜなら、それは誰かに教わるものではなく、自分で選ぶものだからだ。
書き手がどこに立ち、何を見つめたいのか──その在り方こそが、語りのすべてを決めるのだから。
以上
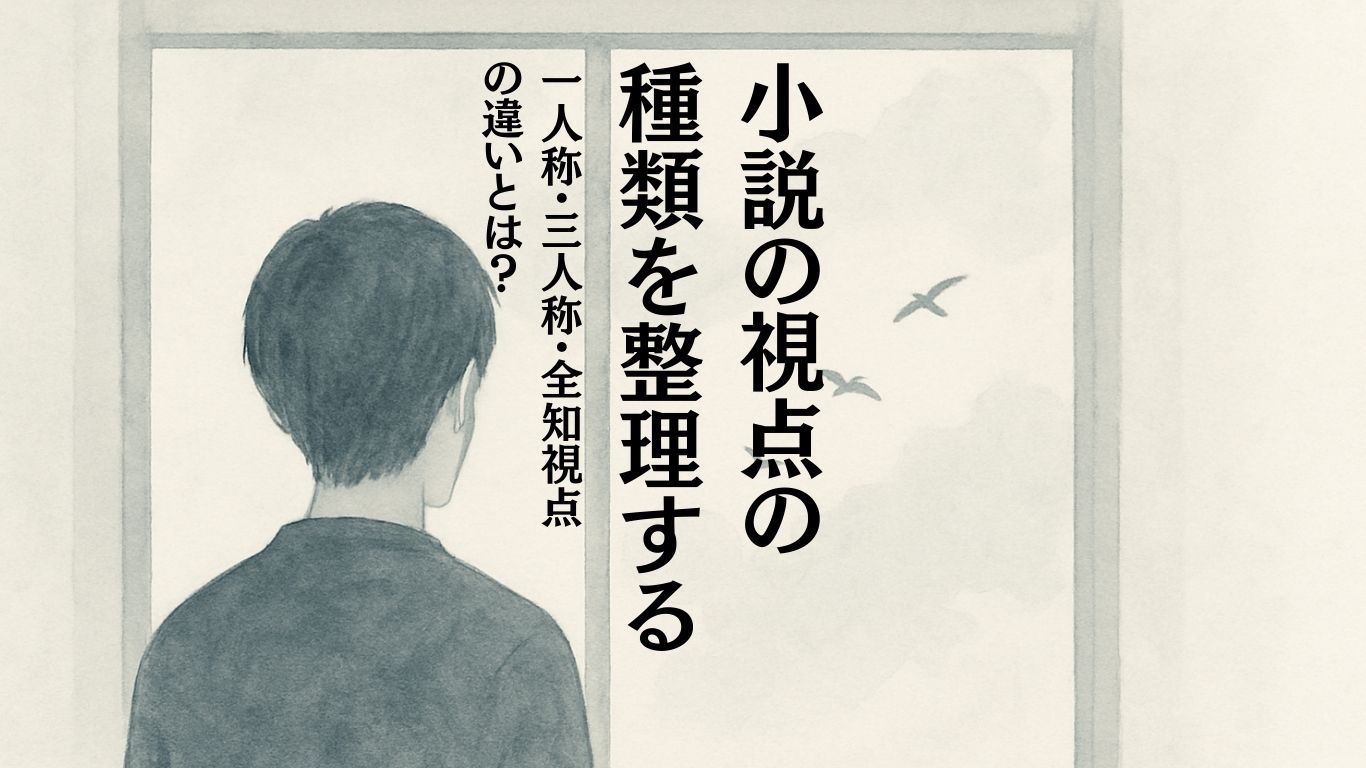
-160x90.jpg)

