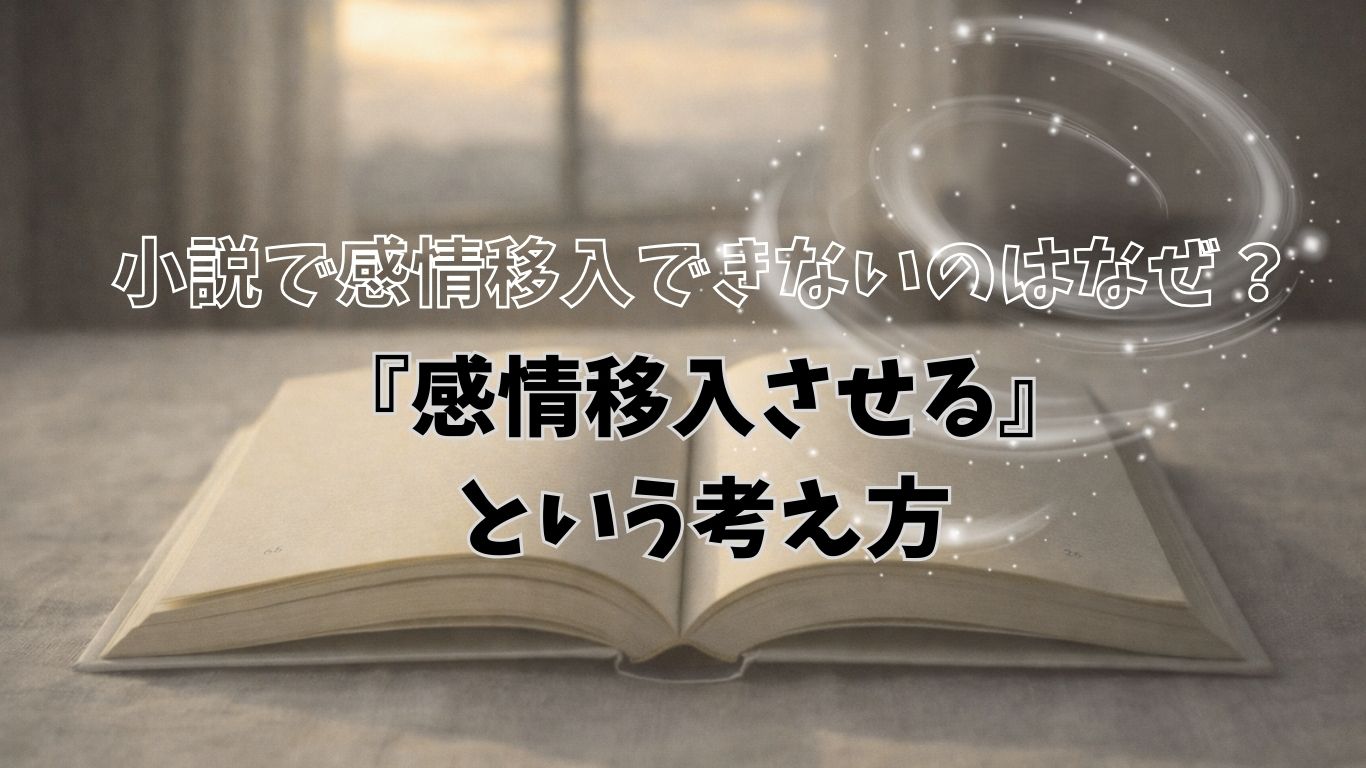小説を読んでいて、登場人物に感情移入できないと感じたことはないだろうか。
周囲が『泣いた』『心を揺さぶられた』と語る作品でも、どこか距離を感じてしまう。そんな体験をすると、自分は読書に向いていないのではないか、と不安になる人も少なくない。
インターネットでは、感情移入は『できたほうが良いもの』であり、『できないのは改善すべき状態』として語られることが多い。
けれど、そもそも感情移入とは、本当に『させられるもの』なのだろうか?
感情移入できないことではなく、読書の語られ方そのものが、読者を一歩引かせている可能性はないだろうか?
まずは、一般的に語られている通説から整理してみたい。
小説は感情移入させるものなのか?
一般的に、小説における感情移入は「読書体験の質」を左右する重要な要素だとされている。
感情移入できる作品は面白く、できない作品は没入できない。そうした前提のもと、『いかに読者を感情移入させるか』という観点で語られることが多い。
その文脈では、いくつかの典型的な技法が紹介される。
たとえば、主人公の一人称視点を用いること、内面描写を増やすこと、読者と年齢や境遇の近いキャラクターを配置することなどだ。また、苦難や葛藤を丁寧に描くことで、読者の共感を引き出しやすくなるとも言われている。
こうした説明では、感情移入は『設計できるもの』『作者側が意図的に起こすもの』として扱われる傾向がある。その結果、読者はいつの間にか『感情移入できたかどうか』で自分の読書体験を測るようになる。
しかし、この考え方には一つの前提が含まれている。それは、読者は作品に感情移入する存在であるべきだ、という暗黙の期待だ。
感情移入できない読者は、読み方が浅いのか、想像力が足りないのか、といった形で自己評価を下げてしまいやすい。
通説の多くは、感情移入を『良い読書の条件』として提示する一方で、感情移入しないまま読む、距離を保って読む、といった読書体験をほとんど想定していない。
その語られ方自体が、読者を受動的な立場に置き、結果として小説との距離を生んでいる可能性も否定できない。
感情移入は委ねること
見出しの問いは、書き手と読み手とで、真逆の意味合いを持つ。
書き手の立場からすれば、読者に感情移入を「させる」書き方が重要だと語られることも多い。
ただ、私はそれらが、ネット記事やSNSのような開かれた場で広く流布されるべきものだとは思っていない。書き手自身の内省や、書き手に向けたクローズドな場所、あるいは書籍の中で語られるべきものだと感じている。
理由は単純で、読者として書物を手に取ったとき、そうした前提を知ってしまうと、感情移入を求められているように感じてしまうからだ。
本来、感情移入は『させる』ものではなく『する』もの。要は、感情移入は、書き手の技法ではなく、読み手の側に委ねられた体験である。
書き手にとっては耳が痛いかもしれない。それでも、自分が書いた作品を読み返したときに、自分自身が何かを感じ取れているのなら、読み手もまた、それぞれの仕方で受け取るものがあるのではないか。
つまりは、読み手を導こうとするよりも委ねること。これこそが、今の時代で忘れられつつある真実なのかもしれない。
――そう信じて書いていたいと思っている。
まとめ
今回は、小説の感情移入に関して通説と筆者の意見を述べた。
すべては――
『感情移入は書き手のモノではなく、読み手のモノである』
これに集約されると考えている。
では、ここで一言。
あなたはどんな作品に感情移入しますか?
この答えは、きっと皆さんの中にあるはず。たとえ思いつかないとしても、それも一つの答えだと、私は思っている。
以上